ごきげんよう、ノアです。
今回はお仕事で必要になりそうなのでWBSを調べてまとめました!
WBS(Work Breakdown Structure)とは
Work Breakdown Structure:作業分解構成図
プロジェクト全体を細かな作業(Work)に分解(Breakdown)した構成図(Structure)になります。
プロジェクトの作業を段階的に細かなタスクに分解して計画を立てて実績を管理することで、プロジェクト全体でやるべき作業を洗い出す際にとても役立つそうです。
WBSは主に2種類あります
- プロセス軸のWBS
- 成果物軸のWBS
プロセス軸のWBS
成果物が不透明な中長期プロジェクトに用います。
プロジェクトの階層に着目し、タスクを細分化・構造化する手法です。
例)自社の離職率を5%低減させる など
成果物軸のWBS
成果物が明確な短期プロジェクトに用いられます。
プロジェクト達成に必要な成果物から逆算してタスクを分解し、順序立ててツリー構造を構築します。
例)システム開発 など
WBSのメリット
WBSを作成することによるメリットはたくさんあります。
やるべき作業の明確化ができます
WBSの特徴は階層構造なので、トップダウン式にタスクを洗い出すことになります。
そうすると、上から順にタスクを洗い出していくので、思いつくままにタスクを並べることはなくなります。
よってタスクが思いつき易く整理されていき、タスクの漏れが防げます。
また、何をすれば良いかどんな作業をしなければならないかが具体化されるので、作業の漏れを防止することができます。
スケジュールが組めます
タスクをガントチャートに表現できます。
そうすると、手際の良い作業手順を組むことができます。
役割を分担できます
タスクが明確になっているので、担当者を割り当てることができます。
また、担当者を明確にできるということは、責任の所在も明確にできます。
(「誰かがやる」ですと、結局誰がやるの?と責任の所在が不明になってしまいますよね、気づいた人がやるは極力やめた方がいいので・・・)
工数見積が可能になります
タスクの分割があまい工数見積は、適当な見積もりになってしまうので誤差が大きくなりがちです。
WBSを作成すると各タスクの規模感が明確になりますので、積み上げて全体の工数が明らかにできます。
進捗管理が可能です
各タスクの進捗状況が明確にできるので、何が遅れているのかを明確にできます。
スコープが明確になります
作業スコープとして何が計画されているのかがプロジェクトメンバーやユーザーに共有することができます。
WBSの作り方
- 成果物・プロセスから逆算し必要な作業を洗い出します
- 作業の粒度・順序を整理します
- 作業の構造化と期日の設定をします
- 各作業に担当者を設定します
成果物・プロセスから逆算し必要な作業を洗い出します
まず、プロジェクトの目的や成果物から逆算し、漏れや重複に注意しながらタスクを洗い出すします。
※必要作業が多い中長期プロジェクトの場合は大まかな作業フェーズごとにタスクを考慮します。
だいたい3階層程度(大項目、中項目、小項目)にまとめます。
プロジェクトの管理工数を8/80ルール(各項目の作業期間を8時間(1日)以上80時間(2週間)未満にすべき)などで考慮し、適度な粒度のタスクを洗い出します。
例)Webサイトを制作するプロジェクトの場合
企画 ・設計・ デザイン制作・ 実装・コーディング・ リリースなど
→ここから作業フェーズをさらに細分化します。
作業の粒度・順序を整理します
洗い出したタスクをいきなり構造化するのではなく、粒度(工数や所要時間のこと)・順序を整理することが重要です。
粒度
粒度にばらつきがあると、構造化した際に歪なツリー構造となってしまい、プロジェクト開始後の進捗管理がごちゃついてしまう恐れもあるためです。
作業の粒度をそろえるために、工数や所要時間を軸にグループ化します。
順序
優先順位の高いタスクが遅延した場合、他の関連タスクのみならずプロジェクト全体にまで影響する恐れがあるため、タスクの依存関係を考慮し順序を整理します。
また、クリティカルパスを設定しておきます。
※クリティカルパス:次のタスクに移るために完成していないといけないタスクや
所要時間が最も長いタスクのことです。
※重要なタスクを一目で把握できるため、プロジェクトの遅延防止にも繋がります。
作業の構造化と期日の設定をします
プロジェクトの流れに沿って作業を構造化します。
親タスク・子タスクの関係性が正常であるか、同階層の業務負担がかけ離れていないかに注意します。そしてツリー構造が完成したのち、各タスクに期日を設定します。
また、想定外の事態(計画段階では気づけなかったタスクやトラブルなど)に備え、期日に余裕を作ります。
各作業に担当者を設定します
各作業に担当者を設定します。
その際、すべてのタスクに担当者を設定します。
責任の所在が曖昧な状態になるような担当者振りはNGです!
ミスやトラブルが生じた場合、迅速に対処し円滑にタスクを遂行するためにも、すべてのタスクに担当者を割り振ります。
WBSを作成する際のポイント
- 目標やゴールを明確にします
- 不明確なタスクは作らないようにします
- クリティカルパスとバッファは分けて考えます
- プロジェクトに余裕を持たせます
- ツールを活用します
目標やゴールを明確にします
目標が曖昧だと不要なタスクを盛り込んでしまうことがあるため、必要なタスクを用意するために目標・ゴールは明確にしましょう。
不明確なタスクは作らないようにします
できるだけタスクの内容を明らかにします。
しかし、正直内容が曖昧なタスクが出てしまうこともあります。タスクの内容がどうしても確定できない場合は、工数を推測で見積もらないようにしましょう。
推測で見積もりを出したタスクが実は膨大な工数に及ぶこともあり得るため、不明確なタスクは確定できない状態で残しておき、実務を進める中で内容を明らかにしていきましょう。
クリティカルパスとバッファは分けて考えます
タスク単位で工数を見積もる場合には、実態に合った工数で算出します。
タスク単位でバッファをもたせてしまうと、工数見積が膨張していってしまうので、クリティカルパスを正確に見極めた上で、必要に応じてバッファを設けます。
プロジェクトに余裕を持たせます
正直、プロジェクトを始めなければ気づけないことは出てきてしまいます。また、プロジェクトを進める中で予想だにしないトラブルが生じることもありますので、万が一に備えた余白を意図的に作りましょう。
予想外の事態が発生した場合に、回避・リカバリーできる状態を想定しWBSを作成します。
ツールを活用します
WBSの作成には、多くの時間・手間がかかりますので、ツールを積極的に活用しましょう。
感想
大きなプロジェクトでは、何からどうすればいいんだ?と不安になってしまいますが、物事はすべて小さいタスクの塊がまとまったものになります。
プロジェクトをタスクとして細かくし、それをひとつづつ潰していくことが前に進むことになるので、WBSはとてもいいものだと思います。そして、誰がやらないといけないのかの責任を明確にすることは本当に大事だと思っているのである程度の規模のプロジェクトなら絶対あった方がいいなと思いました。

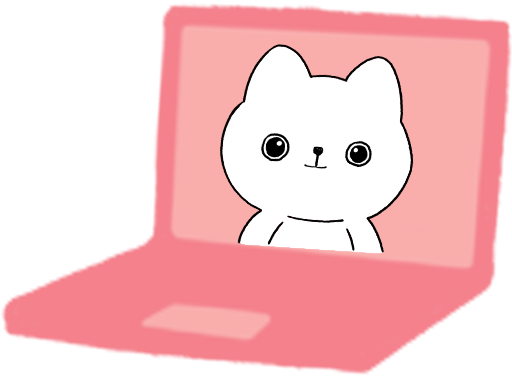
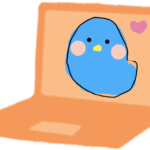

コメント