ごきげんよう、ノアです。
私の今年の目標は『最低限の機能が実装されているシステムを作る』です。
なので現在コツコツ地道に計画を進めております。
IT業界にいるとよく『要件定義』という言葉は聞きますが、要件定義の前に実は『要求定義』というものがあるそうです。
簡単に言えば、「こんなシステムが作りたいから何とかしてよ~」と、システム開発者へ依頼する際の定義書になります(要求定義と要件定義が混ざることも実際は多いそうですが)。
自分自身どんなシステムを作りたいのか整理することも含める意味で、自分自身に要求定義をしてみました。
今回は、要求定義作成時の感想をお話しできたらと思います。
プロジェクトの目的をはっきりさせましょう
まず『なぜ(Why)このプロジェクトを企画したのか』と、目的を明確にする必要がありそうだったのでしっかり文字にしました。
記載しているときにとってもワクワクしました。
要件の内容をはっきりさせましょう
要求定義の際『何がしたいのか(What) 』をはっきりさせる必要があります。
そして「必要な機能のお話」と「機能外」のお話も記載する必要があるそうです。
必須事項を決めましょう
「解決したい課題」・「提供したい機能や仕組み」と『なにがしたいか』を書いていきます。
ここでは具体的なことは極力書かないようにするそうです(※実際要件定義の際まとめるため)。
おそらく非ITの方の方が逆に書きやすいんですかね?どうなんでしょうか。
非機能要件も決めるそうですよ
要求定義の時点でセキュリティ・パフォーマンスなども決めていくそうです。
セキュリティに関してはなんとなくイメージついていましたが、パフォーマンスの部分などもこのタイミングで記載するそうです。
びっくりして慌てて調べました。
実施条件と前提をはっきりと
個人開発なので、「予算はサーバー代、リソースも一人」と、シュールな感じになりました。
システムによっては制約事項とか大変そうだなと感じました。
関係者と役割を明確にしておきましょう
個人開発なので依頼者から責任者まで全部自分になってしまって面白かったです。
でも、実際のシステムだと誰が責任者で誰が窓口になるのか明確にしておかないと責任の所在といいますか、色々大変なことになりそうなのですごい大事なことだと感じました。
リスクと対策もここで提示するらしいです・・・?
リスクと対策は・・・要求定義(非技術者が依頼するための定義)で分かる人はいるんだろうかと疑問にちょっとだけ思いました。
スケジュールは現実的なものを
今回は個人開発なので私の頑張り次第なのですが、本来のシステム開発でしたら現実的なスケジュール設定を考えながら設定する必要があるよねと感じました。
ゴールです!成果物!!
今回、WEBページと、テスト結果を納品することにしました。
テストも後ほど作らないといけませんね。
全体の感想
正直今回は個人開発なので自分のやりたいことは分かり切っているつもりでしたが、要求定義のテンプレートを見ると、自分が思っている以上に「決めておくこと・伝えないといけないこと」があったりして、実際にシステムを作るときは、ちゃんと時間をしっかりとってまとめないといけない工程だなと感じました。
ここでくじけるとプロジェクトが大崩壊するらしいので、責任重大です。肝に銘じておきます。
そして実際作ってみて、自分の頭のフワフワをしっかり形にできてよかったです。
終わりに
正直個人開発なのでコードをいきなり書き始めることも可能なのですが、きっちり順序だてて進めていこうと思い要求定義を作成したわけですが、結果として、個人的にやってみてよかったです。
これ(要求定義)が実際形になるのと思うとワクワクします!
是非皆さんもしっかりとした要求定義を作成し、自分たちの業務が改善したり、新しいサービス作りにワクワクしてくださいませ。
次は要件定義です~!

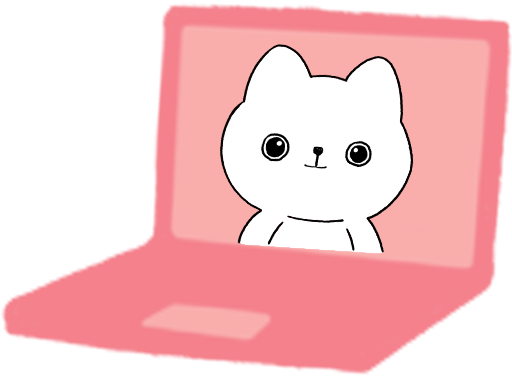
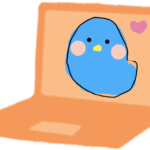
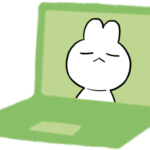
コメント